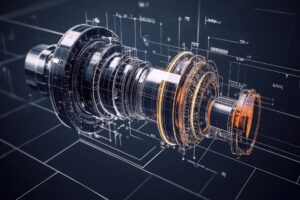自動車・航空認証取得への進め方 – ステップバイステップ

はじめに
自動車・航空宇宙産業の部品製造メーカーにとって、IATF 16949(自動車業界向け)やJIS Q 9100(航空・宇宙業界向け)の認証取得は、ビジネスチャンスを拡大するための大きな鍵です。取引先から要求されることが増え、取得すれば信頼度やブランド力が高まり、大手企業や海外顧客との取引拡大にもつながります。
しかし一方で、認証取得にはコストや労力がかかるのも事実です。
- 人件費(内部監査員・管理担当の育成や配置)
- 教育・トレーニング費用(規格の理解・運用ルールの定着)
- 手順書や文書作成の負担(現場に合わせたカスタマイズ作業)
また、以下のような悩みをお持ちの方は少なくありません。
- 「まず何から手をつければいいのか」
- 「現場が混乱しそうで不安だ」
- 「現場はすでに手一杯で、これ以上の負荷をかけたら反発されるかも…」
- 「ISO9001より難しいと聞くが、実際どの程度の作業量になるのか?」
こういった不安や疑問を抱えて、「認証を取らなければいけないのはわかるけど、どう進めていけばよいのか先が見えない」という声もよく耳にします。実際、当社がご相談を受けるお客様の多くは、“認証取得はしたいが失敗やムダを避けたい”という切実な思いをお持ちです。だからこそ、やみくもに進めるのではなく、全体像を理解したうえでステップを踏むことが大切になります。
この記事では、現役のIATF 16949審査員/JIS Q 9100審査員として10年以上にわたり第一線で審査に携わり、さらに認証機関の責任者としてIATF 16949審査/JIS Q 9100審査全体を統括してきた実績をもつ当社代表が、その豊富な審査経験と知見をもとに、ステップバイステップで認証取得の進め方を解説しつつ、起こりがちな課題やリスクも取り上げます。認証取得の“リアル”を理解し、長期的にメリットを得られるよう、ぜひ最後までお読みください。
 当社代表
当社代表「長年、IATF 16949 / JIS Q 9100の認証を取得される企業を多く見てきました。
認証取得は企業にとって大きなターニングポイントになりますが、その反面、準備不足や形式的な取り組みでかえってコストばかり膨らむケースもあります。
本質を押さえたシステム構築で、認証取得を“通過点”にできるようサポートいたしますので、ぜひ参考にしてみてください。
記事作成のポリシーや工程については、「お役立ち情報をお届けするまで」もぜひご覧ください。
先に内容をまとめると以下となります。
- 全体像を把握し、段階的に取り組む
- 現状把握&目標設定
- 計画立案&導入準備
- 内部監査&是正活動
- 外部審査・認証取得&その後の維持
といった大まかな流れを理解することで、ムダな作業や手戻りを最小限にできます。
- 「なぜ導入するのか?」を社内で共有する
認証を取得する目的を明確にし、現場とトップマネジメント双方のコミットを得ることで、“形式だけ”に終わらない実効性のあるシステムづくりが可能になります。 - 小さな一歩を積み重ねる
現場の声を集めるミーティングや文書類の“短時間チェック”など、すぐにできる行動から始めることで、認証取得の成功率を高められます。必要に応じて外部の専門家やコンサルの力を借りることも選択肢の一つです。 - 取得後こそが本番
認証はあくまでも“通過点”です。取得後の維持審査や改善活動を通じて、システムの運用レベルを高めることが、リスク低減や売上拡大、ブランド価値向上といった成果につながります。
当社の詳細については、「会社概要」でご紹介しておりますので、ご興味があれば併せてご覧ください。
では、詳しく見ていきましょう。
全体像を押さえる:認証取得プロセスの4つのステップ
IATF 16949/JIS Q 9100の認証取得には、大まかに以下の4つのステップがあります。
本記事では、各ステップをさらに小さなプロセスに分解しながら、現場で起こりがちな課題や注意点を交えてご紹介します。
ギャップ分析を含め、認証取得後のあるべき姿を明確に
プロジェクトチーム編成、運用ルール整備、文書化
不適合の洗い出しと改善、監査員の育成
本審査、認証取得、その後の維持と運用
認証はゴールではなくスタートラインです。
ステップ4の後が、「システムを自社の経営や現場にどう根づかせるか?」という本当の勝負どころとなります。
ステップ1:現状把握(ギャップ分析)と目標設定
自社現状の洗い出し

まずは、規格要求と自社の実態を比較し、足りない部分をリスト化しましょう。
- ISO9001をすでに取得している場合は、その差分をチェック
- 品質目標やKPIはどこまで運用されているか
- 工程管理やサプライヤー評価の仕組みは整っているか
- 現場は経験則で回しているが、手順書や記録が不十分 → 「書類作り」が膨大になりがち
- FMEAやコントロールプランなどのツールが形式だけで、実質使われていない
取得のゴールを明確化
「取得で終わり」ではなく、自社が認証をどう活かしたいかを明確にすると、余計な作業やムダを省きやすくなります。
- 例:短期的な売上拡大、リスクマネジメントの強化、長期的なブランド価値アップなど。
 当社代表
当社代表IATFや9100は、ISO9001より要求事項が多岐にわたり複雑です。形だけ整えても現場がついていかず、かえってムダや不満が増えるケースも。
『なぜやるのか?何を目指すのか?』を社内で共有すると、導入後の“腰折れ”を防げますよ。
ステップ2:計画立案&導入準備
プロジェクト体制の編成

- プロジェクトリーダーの選定(品質管理部門or専任プロジェクトチーム)
- 現場リーダーや関連部署との調整役をどう配置するか
- コンサルタント活用の可否(内部リソース不足や専門知識の活用検討)
- 現場への周知不足 → 「なんでこんな面倒なことやらなきゃいけないの?」と反発が起こる
- トップのコミット不足 → 社内の理解・協力が得られず計画が遅延
文書化・運用ルールの整備
- 手順書・規定類の見直しと追加作成
- FMEA、コントロールプランなど、自動車・航空特有の要求事項への対応
- 特採フロー、変更管理プロセスの確立
- 現場の業務実態から乖離した手順書になる
- 書類量が増えすぎて混乱 → 「やってはいるけど結局形だけ」の運用に陥る
現場教育・トレーニング
- 規格の基本概念、要求事項の意図を解説
- 実務に落とし込むワークショップ形式で学習
- 審査の視点を取り入れ、どこが審査で重視されるかを共有
 当社代表
当社代表教育をおろそかにすると、認証が取れた後も“形式だけ”で終わります。最初にしっかり学んでおけば、審査での指摘も少なくなり、トータルコストを抑えられます。
当社では、自動車・航空の現場に特化したトレーニングを実施し、“すぐに使える知識”の習得をサポートします。
ステップ3:内部監査&是正活動

内部監査の計画・実施
- 監査計画を決める
- 監査員の育成(資格要件を満たす人材の確保)
- 現場でのヒアリング・観察実施
- 内部監査員に経験がなく、指摘が浅く表面的 → 実質的な不備が見逃される
- 担当者の兼任が多く、内部監査の日程や準備時間が確保できない
不適合への是正処置とフォロー
- 指摘内容の分析(なぜ起きたのか、再発防止策は何か)
- 改善アクションを社内展開し、効果検証まで追いかける
- 経営視点での整合性(戦略・ブランドイメージとの連動)も考慮
 当社代表
当社代表内部監査は厳しすぎても萎縮が起きますし、甘すぎても意味がありません。適切な評価バランスを取るには、経験豊富な内部監査員の目線が大切です。
当社が提供する“内部監査支援サービス”では、認証要求をしっかり押さえつつ、現場の改善につながる内部監査を実施しています。
外部審査・認証取得とその後の維持

審査前の最終確認(模擬審査など)
- 文書や記録の最終チェック(不備・抜け漏れ)
- 各部署の審査対応準備(規格要求をどこまで理解しているか)
- 模擬審査の実施
- 直前になって現場が「こんな運用聞いてない!」と混乱 → 外部審査で大きな指摘を受ける
- 外部審査当日にキーマンが不在・業務多忙で十分な受け答えができない
認証取得後の維持・改善
- サーベイランス審査(年次審査)や更新審査への対応
- 継続的改善(PDCA)の仕組みを運用し、社内に定着させる
- サプライヤーマネジメント(外注先や協力会社の品質監査・教育)
 当社代表
当社代表認証はあくまで“通過点”で、むしろ取得後にどれだけシステムを使いこなせるかが勝負です。
『システムを入れたけど負担ばかり増えた』なんて声をよく聞きますが、工夫次第でリスク管理・売上拡大・人材育成まで多くのメリットを引き出すことが可能です
取得の先にある「競争優位とブランド価値」:長期的な視点の重要性
IATF 16949 / JIS Q 9100は、世界的に認知された品質マネジメント規格です。取得そのものは大変でも、グローバル企業や大手との取引拡大、リスク低減、長期的なブランド価値向上など、得られるメリットは大きいといえます。
ただし、ネガティブ面を正しく理解し対策しておくことで、結果的に長期的な“費用対効果”は高まります。形式的に導入するよりも、しっかり現場に馴染むシステムを構築したほうが、ムダな再構築費用や手戻りを防げるからです。
ポジティブ面
他社との差別化、優秀な人材獲得、海外市場への進出
ネガティブ面(潜在的リスク)
維持費用、運用負荷、導入時の社内抵抗
今すぐ動ける!アクションポイント
ここまでのステップを踏まえて、「今の段階からすぐに実行できること」をまとめました。自社のフェーズにい合わせて、一歩ずつ取り組んでみてください。
1.情報収集と初期検討
“何が必要か”の情報収集を始め、自社に合った導入形態を検討
・認証機関の公開情報をチェック
・経営層や部署横断で小さな打ち合わせを設定し、「いつまでに何をやるか」の共通認識を図る
・「内製する」「コンサルを活用する」など複数パターンで試算
・予算感・スケジュール感を大まかに洗い出し、経営層への提案材料を作成
2. 計画策定
小さなギャップ分析を始める
・すぐにできる範囲(品質マニュアルや手順書など)から、規格との乖離をチェック
・プロジェクト体制案を作り、関係者の役割分担・スケジュールをざっくり設定
・早めに社内キーマンを巻き込む(トップマネジメント、主要部署リーダーなど)
次に取るべき“小さな一歩”で、認証取得の成功率を高める
認証を取るまでの道のりは長く、業務と並行で進める分、迷いや不安が尽きません。
しかし、”小さな一歩”を踏み出すだけで、失敗やムダを大幅に減らすことができます。例えば次のような取り組みは、比較的すぐに取りかかれるものです。
- 「現場の声」を集めるミーティングを定期開催
- 不満や疑問が顕在化していれば、早めに対策しやすい
- 組織全体が「認証をみんなで取る」という意識に変わる
- 文書や手順を“最短チェック”する時間を設ける
- 複数人で30分読み合わせするだけでも、形式的になっている部分が浮き彫りに
- 細かい変更は徐々にでOK。まずは現場が使えるかどうかを確認
- 外部の力を適宜借りる準備をしておく
- 内部監査だけでなく、模擬審査やコンサル支援など、必要に応じて活用
- 内製と外部支援をうまく組み合わせて、現場負荷をコントロール
こうした“小さな行動”を積み重ねることで、自社の認証取得プロジェクトが「単なるお題目」ではなく、現場と経営を結びつける本質的な取り組みへと進化していきます。ぜひ今できる範囲から手をつけてみてください。
もし、どのフェーズにいるのか判断がつかない、あるいはすでに導入が行き詰まってしまっている場合は、お気軽に当社へご相談ください。当社がしっかり伴走しながら、認証取得を「競争優位の企業づくり」につなげていくお手伝いをいたします。
短期的な認証取得と、長期的な企業価値向上を両立させるために、今こそ一歩踏み出してみましょう。当社は、その一歩を力強くサポートいたします。
次のステージへ – 認証取得以上の価値を生み出すには
IATF 16949/JIS Q 9100の導入は「お客様からの要求に対応する」だけではなく、自社の競争優位を築く絶好の機会になります。
- 品質管理体制を整えることは、市場からの信頼獲得につながり、結果として新規ビジネスの拡大やブランド価値向上にも寄与します。
- 当社では、審査員としての視点+認証機関責任者としてのマネジメント経験を掛け合わせ、単なる手順や書類づくりだけの「形だけの認証」で終わらない「経営戦略としての品質保証体制づくり」を支援しています。
- 認証を取った“後”の運用こそ本番。継続的改善が回り続ける仕組みを作り込むことで、不具合低減・コスト削減・ブランド向上などのメリットを最大限に活かせます。
当社では、以下のような総合サポートを行っています。
- コンサルティングサービス
- 審査員かつ認証機関責任者としての経験をフルに活かし、最短・最適な認証取得とリスク最小化を支援
- 「現場にフィットした品質マネジメントシステム」の構築で、品質をコアとした競争優位を確立
- 認証取得だけで終わらず、売上向上・リスク低減・ブランド強化の三拍子を狙える包括的な品質経営サポート
- トレーニングサービス
- 「机上の理論」に偏らず、実務レベルで使える内容を重視
- 企業文化を尊重しつつ、現場力を高める人材育成プログラムを提供
- IATF 16949/JIS Q 9100への理解を深めながら、短期成果と長期的な企業価値向上を両立
- 内部監査サービス
- 現役の審査員が内部監査員としてアウトソーシング対応
- 担当者の作業負荷を大幅軽減し、外部審査での指摘リスクを最小化
- 監査員育成にも注力し、将来的に社内完結できる監査体制を構築
- サプライヤーマネジメントサービス
- 重大リスクを未然に防止し、サプライチェーン全体の品質基盤を強化
- 生産効率や納期も犠牲にせず、サプライヤーが自律的に改善を継続できる仕組みを構築
- 認証機関との連携も含め、一括でサポートし、OEM/Tier1の業務負担を大幅に軽減
 当社代表
当社代表戦略的に競争優位を獲得することが重要な時代です。IATF 16949/JIS Q 9100導入は“コスト”ではなく“投資”と考えて、長期的なリターンを最大化していきましょう。
当社の詳細については、「会社概要」からご覧いただけます。
今なら30分の無料相談を実施中
- 「どこから手をつければいい?」
- 「本当に自社に認証が必要?」
- 「どの程度の費用・期間がかかる?」
こうした疑問を抱えた方に向け、初回30分の無料オンライン相談を行っています。
30分の無料相談で解決できること
- 自社の現状把握と、必要なギャップ分析の進め方
- システム導入の具体的なイメージ
- 認証取得の手順・費用・期間の目安
- 運用定着や内部監査のサポート内容
まとめ
IATF 16949やJIS Q 9100の認証取得は、取引拡大やブランド価値向上など多くのメリットをもたらす一方で、導入コストや現場負荷の増大というリスクも伴います。大切なのは、認証そのものをゴールにせず、“自社の経営や現場にどう根づかせるか”を意識した取り組みを行うことです。
- 全体像を把握し、段階的に取り組む
- 現状把握&目標設定
- 計画立案&導入準備
- 内部監査&是正活動
- 外部審査・認証取得&その後の維持
といった大まかな流れを理解することで、ムダな作業や手戻りを最小限にできます。
- 「なぜ導入するのか?」を社内で共有する
認証を取得する目的を明確にし、現場とトップマネジメント双方のコミットを得ることで、“形式だけ”に終わらない実効性のあるシステムづくりが可能になります。 - 小さな一歩を積み重ねる
現場の声を集めるミーティングや文書類の“短時間チェック”など、すぐにできる行動から始めることで、認証取得の成功率を高められます。必要に応じて外部の専門家やコンサルの力を借りることも選択肢の一つです。 - 取得後こそが本番
認証はあくまでも“通過点”です。取得後の維持審査や改善活動を通じて、システムの運用レベルを高めることが、リスク低減や売上拡大、ブランド価値向上といった成果につながります。
短期的な“取得”と長期的な“企業価値向上”の両方を見据え、今できる行動から着実に進めていきましょう。もし導入に行き詰まった際には、専門家やコンサルタントを活用しながら、自社の強みに合った運用システムを構築することが重要です。これらを踏まえ、認証を“単なる条件”ではなく“競争優位の源泉”として活かしていくために、まずは第一歩を踏み出してください。
IATF 16949/JIS Q 9100でお悩みではありませんか?

当社では、「認証取得」だけでなく、売上アップ・リスク低減・ブランド強化まで見据えたコンサルティングサービスを提供しています。顧客要求が厳しい自動車や航空機産業で数多くの経験に基づき、現場で負担なく運用できる仕組みづくりを徹底的にサポートいたします。
もし、「うちの現場にも当てはめたいけれど、具体的に何から着手すれば…?」とお悩みでしたら、ぜひ初回30分の無料相談をご利用ください。
当社の詳細については、「会社概要」からご覧いただけます。
さらに学びたい方へ
FMEAのポイントを押さえて、
品質リスクを
事前に防ぎませんか?
効果的なFMEAの作り方や
運用ノウハウをわかりやすく
解説しています。

内部監査で是正処置の効果と有効性をしっかりと確認できていますか?
是正処置の有効性を検証する
内部監査の進め方を
分かりやすく解説しています。
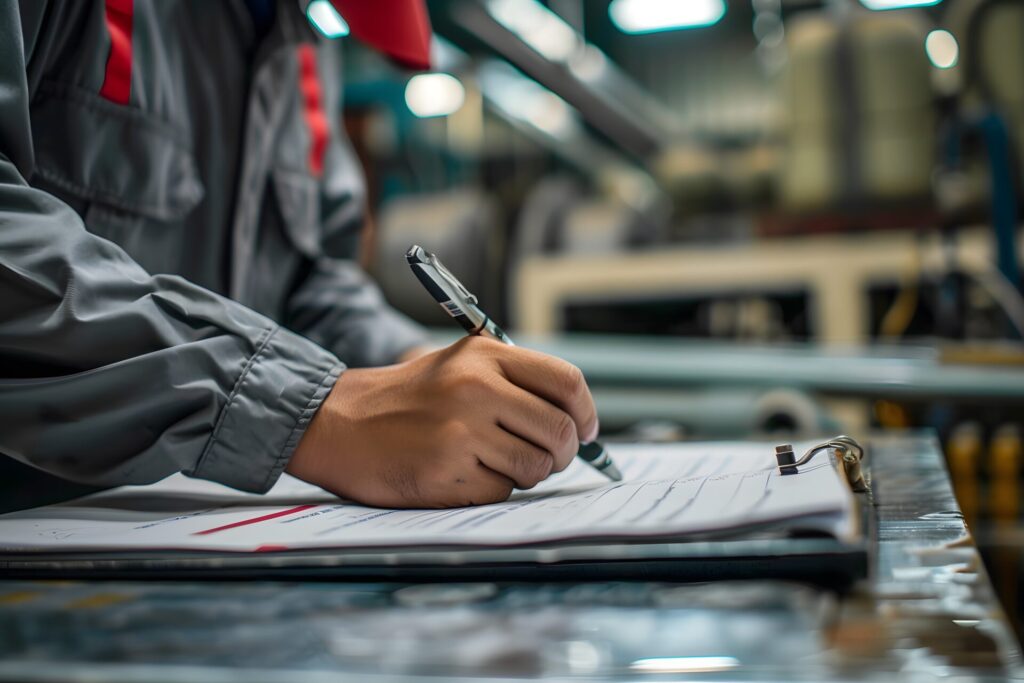
航空・宇宙・防衛分野で
最も広く使われている
JIS Q 9100とは?
JIS Q 9100認証を
取得するメリットや要求事項を
詳しく解説しています。

IATF 16949やJIS Q 9100に関する【お役立ち情報】を、他にも多数ご用意しています。
わかりやすい解説や、役立つノウハウを多数掲載していますので、ぜひ以下のページもご覧ください。
お役立ち情報一覧」を見る