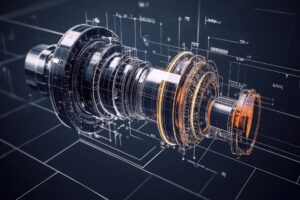APQPを上手く回す秘訣 – バタバタな新製品の立ち上げから脱却へ

はじめに
この記事は、新製品の立ち上げや工程の設計開発を進める中で、以下のようなお悩みをお持ちの方に向けて作られています。
- 新製品の立ち上げが毎回バタバタで、納期ギリギリになってしまう…
- リソースやコスト不足に悩まされながらも、顧客からの厳しい要求に答えなければならない…
- 他部署との調整に多くの時間を割かれて、計画どおりにプロジェクトが進みにくい…
- 不確定要素が多く、計画通りに進めるのが難しい…
もし、こうした悩みをお持ちなら、それは決して珍しいことではありません。新製品立ち上げや新規プロジェクト管理では、さまざまな不確定要素や複数部門との連携が絡み合い、スムーズに進めるのが難しいと感じる方が多いです。自身もそうでしたが、納期が迫る中、計画通りに進まなかったり、予期せぬ変更が発生すれば、焦りや強烈なプレッシャーを感じますよね。しかし、だからといって、毎回ギリギリで焦るばかりでは、自分自身やチームの働きが正当に評価されるチャンスを逃してしまうかもしれません。
そこで、この記事では、現役のIATF 16949審査員として10年以上にわたり第一線で審査に携わり、さらに認証機関の責任者としてIATF 16949審査全体を統括してきた実績をもつ当社代表が、その豊富な審査経験と知見をもとに、自動車産業の品質マネジメントシステム要求であるIATF 16949で活用されているプロジェクト管理手法 APQP (Advanced Product Quality Planning:先行製品品質計画)について解説します。APQPを上手く回して新製品立ち上げをスムーズに進めるためのヒントを、ぜひ、あなたのプロジェクト管理にお役立てください。
記事作成のポリシーや工程については、「お役立ち情報をお届けするまで」もぜひご覧ください。
先にまとめると以下となります。
- APQP (Advanced Product Quality Planning:先行製品品質計画)はIATF 16949の製品と工程の設計において、プロジェクトマネジメントをどのように進めるかを示したガイダンス文書で、全体の段階的な計画、必要なアウトプット(成果物)、その管理に必要な手法について述べられています。
- リスクマネジメントの考え方を取り入れた効果的なプロジェクト管理を行えるため、新製品立ち上げをスムーズに進められる効果的なプロジェクト管理を行うことができます。一方、問題が明らかになるのがプロジェクトの後半になることが多い点、計画立案以降の顧客の要求や仕様変更の変更に弱い点もあります。
- 全体を5つのフェーズに分け、新製品立ち上げをスムーズに進めていきます。具体的には、①プロジェクトの計画、②製品の設計と開発、③工程の設計と開発、④製品と工程の妥当性確認、⑤生産と継続的改善に分けます。
- 上手く管理するには、計画段階での明確な目的と目標設定と要求事項の定義をしっかりと行い、部門横断的なコミュニケーションとレビューを円滑にし、柔軟な対応と変更管理に備え、リスクを可視化したリスクマネジメントを積極的に実施することが必要となります。
当社の詳細については、「会社概要」でご紹介しておりますので、ご興味があれば併せてご覧ください。
では、ここから詳しく見ていきましょう。
APQP (Advanced Product Quality Planning:先行製品品質計画)とは?

APQPは自動車産業の品質マネジメントシステム要求であるIATF 16949の製品と工程の設計において、プロジェクトマネジメントをどのように進めるかを示したガイダンス文書です。
自動車産業で広く利用されており、自動車メーカーが期待する管理方法を企業やそのサプライヤーが理解できるように共通フレームワークとして作られました。
全体の段階的な計画、必要なアウトプット(成果物)、その管理に必要な手法について述べられており、リスクマネジメントの考え方が組み込まれているのが特徴です。
APQPの誕生の経緯
アメリカの自動車メーカーであるGM、フォード、クライスラーが共同で開発し1994年に発行しました。
彼らが満足する製品を保証するために必要な共通のガイダンスをサプライヤーに示すために作られました。
自動車産業の品質マネジメントシステム要求を示したIATF 16949の原型であるQS-9000も同じ時期に発行されており、そこでAPQPを含むコアツールを参照することが示されました。
IATF 16949の詳細については、以下の記事をご確認ください。
航空宇宙分野への適用
1994年に自動車産業で生まれたAPQPは現在、自動車産業で広く普及しています。
さらに、近年では航空宇宙防衛分野においてもAPQPを取り入れようとする動きがあります。
自動車産業で成功を収めているプロジェクトマネジメント手法を学ぶことで、航空宇宙産業で課題となっている機体を納期通りに引き渡す納期遵守パフォーマンスを改善したい意向があるものと思われます。
航空宇宙防衛分野の品質マネジメントシステム要求を記載したJIS Q 9100の次期改訂案としてAPQPが検討されています。
JIS Q 9100の詳細については、以下の記事をご確認ください。
APQPの特徴

強み
- リスクマネジメントの徹底
プロジェクトの初期段階から品質・コスト・納期に影響を与えるリスクを洗い出し、早期に対策を講じられます。 - 段階的なフェーズ管理
5つのフェーズに分けてプロジェクトを進行するため、各段階で必要な成果物や承認プロセスが明確化され、計画的な進行が可能です。 - コスト削減・品質向上
後戻りを最小化し、量産開始後の品質トラブルを未然に防止。顧客から信頼される可能性が高まります。
弱み
- 後半で問題が発覚しやすい
設計検証活動が後半に計画されることが多く、最終段階で大きなリスクや不具合が発覚すると、スケジュールに大きな影響が出ます。 - 変更管理に弱い
計画立案後の顧客要求や仕様変更に対して、想定以上の手戻りが発生しがちです。 - コミュニケーション不足による遅延
部門間調整が不十分だと、計画自体が形骸化し、実際の進捗が見えづらいという課題が生じやすいです。
APQPの進め方:5つのフェーズ
APQPは、大きく以下の5フェーズに分かれています。各フェーズで明確な成果物(アウトプット)が設定されており、フェーズ間のレビューと承認を繰り返すことで、スムーズにプロジェクトを進めるのが基本です。
製品や工程の顧客要望及び計画を明らかにして、プロジェクトの目的・目標・計画を定めます。
顧客の要望及び計画、製品や工程の前提条件を明確化して、全体のプログラムと成果物とスケジュールを示したプロジェクト計画書、製品の要求、目標、暫定の材料や部品のリスト、暫定の工程フロー、リスク分析結果をアウトプットします。
顧客のスケジュールに同期した全体計画となっているか、期日と責任者が明確になっているか、社内とサプライヤーも同意できているかなどを確認します。
 当社代表
当社代表必要な支援が十分に得られるよう、経営層がプロジェクトの計画と進捗をレビューできるようにしておくことが重要です。
顧客の要求を満たし製造できる製品を設計します。
DFMEA, 図面、技術仕様書、特殊特性、設計検証記録、デザインレビュー、設備・計測装置・治工具の要求事項、製品実現性報告書などをアウトプットします。
必要なアウトプットがすべて出されているか、アウトプットは部門横断的にレビューされてリスクマネジメントされているかを確認します。最終的に顧客の納期通りに製品を引き渡すことができるかを明らかにし、必要に応じて経営層から支援を受けます。
効果的な工程とその管理内容を総合的に設計します。
工程フロー図、PFMEA、フロアレイアウト、先行のコントロールプラン、作業指示書、工程能力調査計画書をアウトプットします。
工程は明確になっており、必要な人・設備・管理が準備されているかを確認します。
顧客の要求を満たした製品を生産できることを確認し、それを顧客に示し承認を受けます。
量産コントロールプラン、PPAP、MSA、工程能力調査をアウトプットします。
実際の工程で生産を行い、製品と工程の妥当性を評価します。顧客要求を満足した生産ができることを顧客に示し承認を得ます。
APQPの目的を達成しているかを確認し、効果が上がるようにつなげます。
製品の品質と納期の遵守、工程変動の減少、学んだ教訓を次に生かすといったパフォーマンスをアウトプットします。
品質と納期は顧客要求を満足しているか、工程の品質目標が達成できているかを監視し、満たしていなければ是正処置を実施します。学んだ教訓を明確にして、それが社内で活かされているかを確認します。
各フェーズのポイント:
- フェーズごとに必要な文書やレビュー項目を部門横断的にチェックする
- 変更が発生した場合は、影響範囲の再評価を確実に行い、計画を修正
- 経営層や顧客の承認を得ることで、意思決定のスピードアップやリソース確保がしやすくなる
APQPを上手く管理するための5つのポイント

明確な目標設定と要求事項の定義
計画フェーズではプロジェクトの目的、品質・コスト・納期に関する要求と目標を明確に設定することが大切です。
顧客の要求事項をしっかりと確認したうえで定義しましょう。ここがしっかりしていると、顧客から「よくこちらの意図を汲んでくれていますね」と評価される下地になります。
 当社代表
当社代表成果を最大化できるよう、他社では無理で自社しか達成できない自社ならではの強みをどのように活かすかをプロジェクトの目的に定めることを強くお勧めします。
コミュニケーション
顧客やプロジェクトチーム内で、情報を円滑に伝達するためのルートを予め定めておきます。
これは、APQPの目標である「計画を予定通り完了させる」ために重要だからです。チーム内で円滑なコミュニケーションを図ることで、迅速な意思決定や問題解決が可能になります。
プロジェクトの定例ミーティングや顧客との定期的な打ち合わせについては、どのくらいの頻度で行うか、誰が参加するか、また、会議内容をどのようにしてプロジェクトチーム全体に共有するかなどを事前に決めておくことが大切です。例えば、「毎週定例会議を行い、会議の内容は担当者がプロジェクト全体に共有する」といった具体的な方法を決めておくと良いでしょう。
柔軟な対応と変更管理
進行中の要件の変化に対応できる柔軟性を持たせ変更管理を行います。
変更は起きるものだと想定して、変更が発生した場合のプロジェクト管理の方法を予め定めておき、影響を適切に評価し計画を修正できるようにしておきます。
 当社代表
当社代表製品や機能を検証しやすいレベルまで細分化することがポイントです。チームは設計活動を回しやすくなります。
リスクマネジメント
予防処置として、品質・コスト・納期に影響を与える可能性のあるリスクを積極的に特定し対応策を計画します。
部品の調達リスクや技術的なリスクなどを影響と原因に分けて考え、部門横断チームでレビューすることによって、優先すべきリスクを特定し軽減を図りましょう。優先度が高いリスクには早期に対策を講じ、プロジェクト全体のリスクを低減させます。
リスク対応をちゃんと実行していることを示すことで、「リスクマネジメントがしっかり機能している企業ですね」と顧客にも安心してもらえます。
スケジュール管理
マイルストーンを設定し、各段階での成果物と責任者、期日を明確にし進捗状況を定期的に確認します。
遅延をタイムリーに捉えて、リカバリ策を立案し、スケジュールを修正する柔軟性を持ちましょう。
 当社代表
当社代表多くの企業様を拝見した中で、APQPで特に課題になりやすいのは”変更管理”と“リスクマネジメントの曖昧さ”です。計画段階での想定が甘いと、後半で多くの問題が噴出し、一気にコスト増・納期遅延の要因となるので要注意です。
次のステージへ – 認証取得以上の価値を生み出すには
IATF 16949やJIS Q 9100の導入は「お客様からの要求に対応する」だけではなく、自社の競争優位を築く絶好の機会になります。
- 品質管理体制を整えることは、市場からの信頼獲得につながり、結果として新規ビジネスの拡大やブランド価値向上にも寄与します。
- 当社では、審査員としての視点+認証機関責任者としてのマネジメント経験を掛け合わせ、単なる手順や書類づくりだけの「形だけの認証」で終わらない「経営戦略としての品質保証体制づくり」を支援しています。
- 認証を取った“後”の運用こそ本番。継続的改善が回り続ける仕組みを作り込むことで、不具合低減・コスト削減・ブランド向上などのメリットを最大限に活かせます。
当社では、以下のような総合サポートを行っています。
- コンサルティングサービス
- 審査員かつ認証機関責任者としての経験をフルに活かし、最短・最適な認証取得とリスク最小化を支援
- 「現場にフィットした品質マネジメントシステム」の構築で、品質をコアとした競争優位を確立
- 認証取得だけで終わらず、売上向上・リスク低減・ブランド強化の三拍子を狙える包括的な品質経営サポート
- トレーニングサービス
- 「机上の理論」に偏らず、実務レベルで使える内容を重視
- 企業文化を尊重しつつ、現場力を高める人材育成プログラムを提供
- IATF 16949やJIS Q 9100への理解を深めながら、短期成果と長期的な企業価値向上を両立
- 内部監査サービス
- 現役の審査員が内部監査員としてアウトソーシング対応
- 担当者の作業負荷を大幅軽減し、外部審査での指摘リスクを最小化
- 監査員育成にも注力し、将来的に社内完結できる監査体制を構築
- サプライヤーマネジメントサービス
- 重大リスクを未然に防止し、サプライチェーン全体の品質基盤を強化
- 生産効率や納期も犠牲にせず、サプライヤーが自律的に改善を継続できる仕組みを構築
- 認証機関との連携も含め、一括でサポートし、OEM/Tier1の業務負担を大幅に軽減
 当社代表
当社代表戦略的に競争優位を獲得することが重要な時代です。IATF 16949導入は“コスト”ではなく“投資”と考えて、長期的なリターンを最大化していきましょう。
当社の詳細については、「会社概要」からご覧いただけます。
今なら30分の無料相談を実施中
- 「どこから手をつければいい?」
- 「本当に自社に認証が必要?」
- 「どの程度の費用・期間がかかる?」
こうした疑問を抱えた方に向け、初回30分の無料オンライン相談を行っています。
30分の無料相談で解決できること
- 自社の現状把握と、必要なギャップ分析の進め方
- システム導入の具体的なイメージ
- 認証取得の手順・費用・期間の目安
- 運用定着や内部監査のサポート内容
まとめ
自動車産業の品質マネジメントシステム要求であるIATF 16949で活用されているプロジェクト管理手法 APQP (Advanced Product Quality Planning:先行製品品質計画)について解説しました。
- APQP (Advanced Product Quality Planning:先行製品品質計画)はIATF 16949の製品と工程の設計において、プロジェクトマネジメントをどのように進めるかを示したガイダンス文書で、全体の段階的な計画、必要なアウトプット(成果物)、その管理に必要な手法について述べられています。
- リスクマネジメントの考え方を取り入れた効果的なプロジェクト管理を行えるため、新製品立ち上げをスムーズに進められる効果的なプロジェクト管理を行うことができます。一方、問題が明らかになるのがプロジェクトの後半になることが多い点、計画立案以降の顧客の要求や仕様変更の変更に弱い点もあります。
- 全体を5つのフェーズに分け、新製品立ち上げをスムーズに進めていきます。具体的には、①プロジェクトの計画、②製品の設計と開発、③工程の設計と開発、④製品と工程の妥当性確認、⑤生産と継続的改善に分けます。
- 上手く管理するには、計画段階での明確な目的と目標設定と要求事項の定義をしっかりと行い、部門横断的なコミュニケーションとレビューを円滑にし、柔軟な対応と変更管理に備え、リスクを可視化したリスクマネジメントを積極的に実施することが必要となります。
これらをしっかり押さえておけば、バタバタした新製品立ち上げから脱却し、スムーズなプロジェクト運営が可能になります。
もし、「もっと具体的に支援してほしい」「IATF 16949の取得・運用で悩んでいる」という場合は、ぜひ当社の専門家へのご相談をご検討ください。APQPをフル活用し、貴社の競争力強化につなげましょう。
IATF 16949/JIS Q 9100やAPQPでお悩みではありませんか?

当社では、「認証取得」だけでなく、売上アップ・リスク低減・ブランド強化まで見据えたコンサルティングサービスやトレーニングサービスを提供しています。顧客要求が厳しい自動車や航空機産業で数多くの経験に基づき、現場で負担なく運用できる仕組みづくりを徹底的にサポートいたします。
もし、「うちの現場にも当てはめたいけれど、具体的に何から着手すれば…?」とお悩みでしたら、ぜひ初回30分の無料相談をご利用ください。
当社の詳細については、「会社概要」からご覧いただけます。
もっと学びたい方へ
FMEAのポイントを押さえて、
品質リスクを
事前に防ぎませんか?
効果的なFMEAの作り方や
運用ノウハウをわかりやすく
解説しています。

内部監査で是正処置の効果と有効性をしっかりと確認できていますか?
是正処置の有効性を検証する
内部監査の進め方を
分かりやすく解説しています。
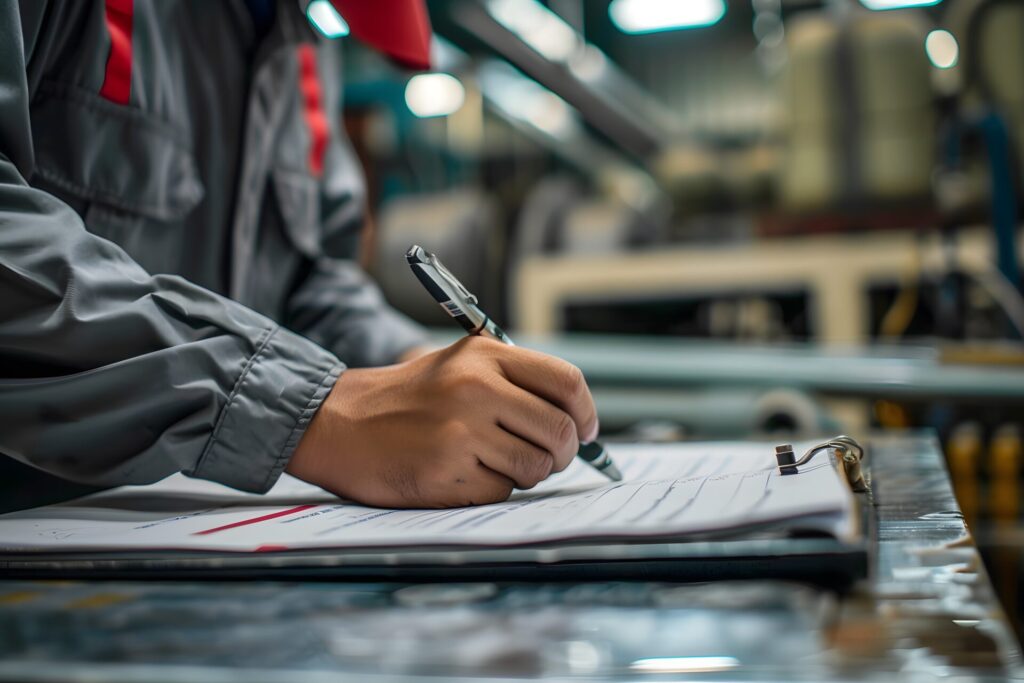
顧客からスムーズに承認されるコントロールプランの書き方を学びませんか?
実運用を踏まえて、コントロールプランの作成ポイントをわかりやすく解説しています。

IATF 16949やJIS Q 9100に関する【お役立ち情報】を、他にも多数ご用意しています。
わかりやすい解説や、役立つノウハウを多数掲載していますので、ぜひ以下のページもご覧ください。
お役立ち情報一覧」を見る